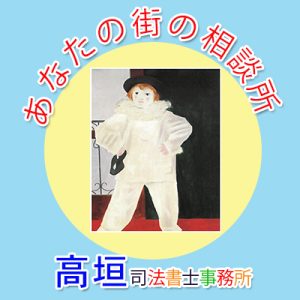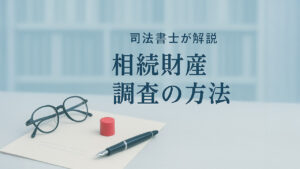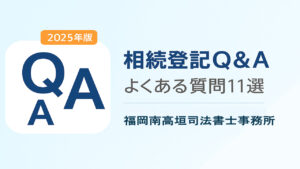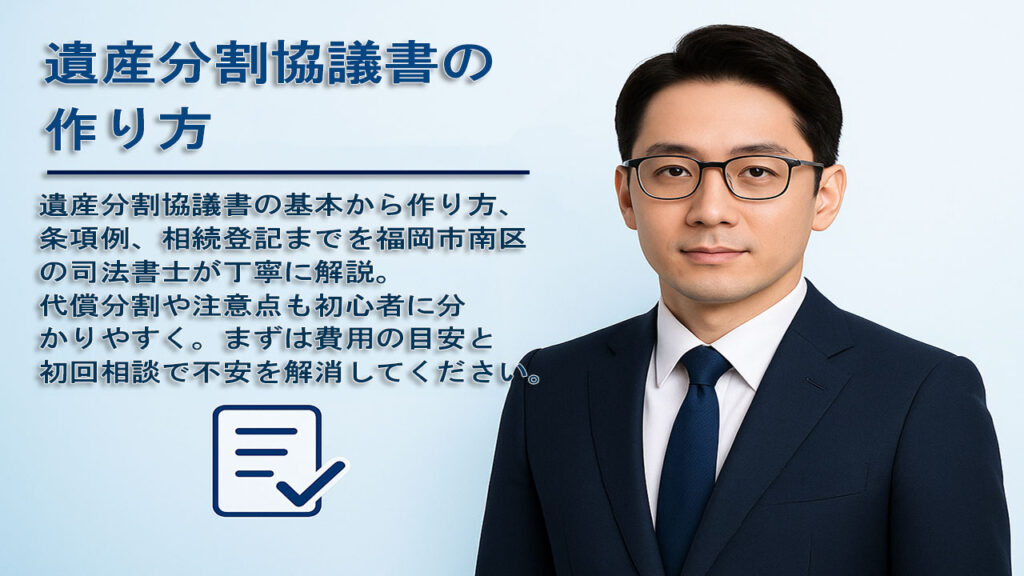
目次
遺産分割協議書の作り方|福岡市南区の司法書士がやさしく解説
相続が発生したら、相続人全員で話し合い、その合意内容を文書化した遺産分割協議書が重要になります。口頭合意だけでは相続登記や金融機関手続で不備が生じやすく、将来の紛争予防の観点からも書面化は必須です。福岡市南区・大橋の福岡南高垣司法書士事務所が、実務に基づいて分かりやすく解説します。
遺産分割協議書とは?基本と目的
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証拠化し、相続登記や金融機関手続をスムーズに進めるための文書です。私文書として作成するのが一般的ですが、内容や紛争リスクに応じて公正証書遺言の活用や公正証書化を検討する場合もあります。
- 形式:私文書(相続人全員の署名・実印押印/印鑑証明書添付が通例)
- 前提:相続人が一人でも欠けると無効になり、登記や解約が進みません
- 添付:印鑑証明書(発行後3か月以内を求められることが多い)
作成の流れ(6ステップ)
ステップ1:相続人と相続財産の確定
被相続人の出生から死亡までの連続戸籍を収集し相続人を確定。相続人各自の戸籍・住民票も揃えます。 相続放棄を予定する場合は家庭裁判所の手続が必要です(期限に注意)。詳しくは 相続放棄の解説をご覧ください。
- 不動産:登記事項証明書/固定資産評価証明書
- 預貯金:残高証明や通帳写し
- その他:有価証券、借入金、クレジット債務など
ステップ2:分割方法の基本方針を決める
- 現物分割:自宅は長男、預金は長女など
- 代償分割:不動産は長男、他相続人へ代償金を支払う
- 換価分割:不動産を売却し代金を按分
共有の継続は将来トラブルの種になりがちです。二次相続も見据えた設計を。
ステップ3:合意内容を条文化する
本文に最低限、次を明確に記載します。
- 被相続人の氏名・本籍・死亡日
- 相続人全員の住所・氏名・生年月日
- 財産の特定と取得者(不動産は所在・地番/家屋番号等、預貯金は口座情報)
- 代償金の金額・期限・方法(該当時)
- 税・引渡し等の実務条項、清算条項
ステップ4:相続人全員の署名・押印
各相続人が自署・実印押印。複数ページは割印で改ざん防止を。
ステップ5:相続登記・金融機関手続
不動産を取得した方は、所在地管轄法務局へ相続登記(名義変更)を申請します。 手続きの全体像は 相続登記(固定ページ) をご参照ください。 預貯金等は各機関の所定書式とともに協議書を提出します。
ステップ6:原本保管と写し配布
原本は厳重保管し、相続人各自に写しを配布しておくと安心です。
つまずきやすいポイントと対策
条項構成のひな形(例)
【構成例】
- 前文(被相続人の表示)
- 第1条:不動産の帰属
- 第2条:預貯金等の帰属
- 第3条:代償金
- 第4条:費用負担・引渡し等
- 第5条:清算条項
- 付記:各相続人の住所・氏名・生年月日/署名押印欄
※テンプレートは個別事情により危険も。二世帯住宅・事業用資産・借入金等が絡む場合は、個別設計をご提案します。
相続登記までワンストップで進めるメリット
- 手戻りゼロ:戸籍収集〜協議書〜登記を一括で設計
- 実務要件を反映:金融機関・法務局の要件を踏まえた安全な条項づくり
- 税務連携:必要に応じ税理士と連携し評価・代償金も現実的に設計
- 迅速対応:相続後の生活再建をスピードサポート
よくある質問(FAQ)
押印は実印が必要ですか?
相続人の一人が遠方にいます。
未分割の財産が後から見つかった場合は?
まずは早めにご相談ください
遺産分割協議書は将来の安心と手続のスムーズさを左右する重要書類です。福岡市南区大橋の福岡南高垣司法書士事務所では、実務要件を踏まえた安全な協議書作成と相続登記までのワンストップ支援を行っています。 費用の目安や 初回相談について、お気軽にご相談ください。