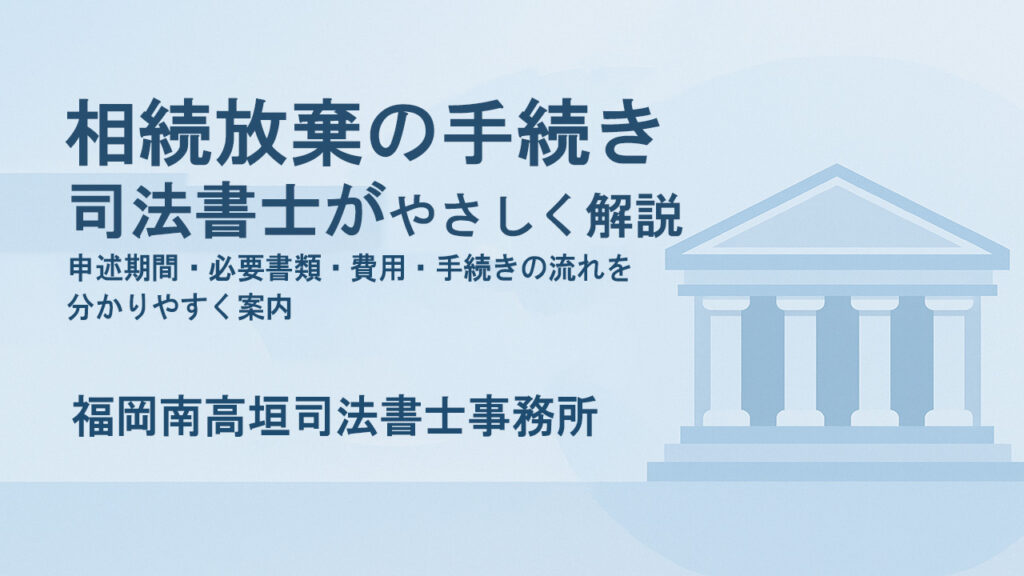福岡市南区・大橋の司法書士
相続放棄の手続き|司法書士がやさしく解説
「借金は相続したくない」「期間に間に合うか不安」——
福岡南高垣司法書士事務所が、申述期間・必要書類・費用・流れを分かりやすくご案内します。
1. 相続放棄とは(概要)
相続が開始したとき、相続人は次のいずれかを選択します。
単純承認
財産も借金もすべて引き継ぐ手続。プラス・マイナスを含めて承継します。
相続放棄
被相続人の権利・義務を一切承継しない手続。借金対策で選ばれることが多いです。
限定承認
相続で得た財産の範囲内でのみ債務を負担。債務額が不明なとき等に検討します。
相続放棄・限定承認はいずれも家庭裁判所への申述が必要です。ここでは相続放棄を中心に解説します。
2. 申述人(だれができる?)
- 相続人ご本人(未成年者・成年被後見人の場合は法定代理人が代理)
- 未成年者とその法定代理人が共同相続人の場合などは、特別代理人の選任が必要になることがあります。
3. 申述期間(3か月ルール)
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に行います。
財産が全くないと信じていた等、例外的に受理されるケースもありますが、原則は厳格です。早めのご相談をおすすめします。
4. 申述先(家庭裁判所)
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
※ 管轄の確認で迷われたら当事務所にご相談ください。
5. 申述に必要な費用
- 収入印紙:800円(申述人1人につき)
- 郵便切手:連絡用(裁判所により異なります) ※各家庭裁判所の案内をご確認ください。
6. 必要書類
相続放棄の申述書に加えて、次の書類が必要です(同一事件で提出済みのものは不要な場合があります)。
【配偶者・子】
- 申述人の(相続放棄される方)戸籍謄本(あるいは、戸籍の全部事項証明書)1通
- 被相続人の住民票の除票(あるいは、戸籍の附票)1通
- 被相続人の死亡の旨、記載のある戸籍謄本1通
【代襲相続人の場合】
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨記載のある戸籍謄本1通
【父母・祖父母(第二順位)】
- 申述人の戸籍謄本(あるいは、戸籍の全部事項証明書)1通
- 被相続人の住民票の除票(あるいは、戸籍の附票)1通
- 被相続人の出生時に初めて載った戸籍謄本から死亡の旨記載のある戸籍謄本まで、被相続人が載っている戸籍謄本すべて(出生時から死亡時までつながるように「全部」提出してください。)各1通
【兄弟姉妹】
- 申述人の戸籍謄本(あるいは、戸籍の全部事項証明書)1通
- 被相続人の住民票の除票(あるいは、戸籍の附票)1通
- 被相続人の出生時に初めて載った戸籍謄本から死亡の旨記載のある戸籍謄本まで、被相続人が載っている戸籍謄本すべて(出生時から死亡時までつながるように「全部」提出してください。)各1通
- 直系尊属が死亡している場合には 死亡の旨記載のある戸籍謄本各1通
【代襲相続人の場合】
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の旨記載のある戸籍謄本1通
※ 戸籍等の名称は「全部事項証明書」と表記されることがあります。必要書類の事前入手が難しい場合、申述書を出しておけば3か月経過後の追加提出でも差し支えない場合があります。審理で追加書類を求められることもあります。
7. 期間の伸長(やむを得ないとき)
3か月以内に財産調査をしても判断資料が揃わない場合、期間伸長の申立てにより家庭裁判所が期間を延長できる制度があります。
8. よくある質問(Q&A)
Q. 夫が数年前に亡くなっています。今から相続放棄はできますか?
相続放棄は原則として知ってから3か月以内ですが、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある等、例外的に受理されることがあるとされています。個別事情により判断が分かれますので、まずはご相談ください。
Q. 受理後は何をすれば良いですか?
管理している財産がある場合は相続人へ引継ぎます。債権者から請求を受けているときは、相続放棄受理の事実を連絡するとよいでしょう。
Q. 受理証明書はどうやって取りますか?
家庭裁判所の申請用紙に記入し、1件150円の収入印紙と(郵送なら)返信用切手を添付して申請します。来庁の場合は印鑑と本人確認書類をご持参ください。
9. 手続の流れ(当事務所・福岡家庭裁判所の場合)
- 申述書の作成:申述人欄は直筆署名。年齢・職業も記入。
- 提出:必要書類と合わせて福岡家庭裁判所へ郵送。
- 照会書の受領:到着後7〜10日程度で各申述人に照会書が届きます(時期は変動)。
- 記入・返送:単純法定承認理由は「ない」、相続放棄はご本人の意思かは「はい」で回答。押印は申述書と同じ印鑑を使用。
- 受理通知書の受領:返送後約1週間で相続放棄受理通知書が届き、手続完了。
※ 再発行はできません。厳重に保管してください。債権者からは受理通知書のコピー、または受理証明書(1通150円・郵送可)の提出を求められる場合があります。
※ 場合により照会書なしで直接、受理通知書が届くこともあります。