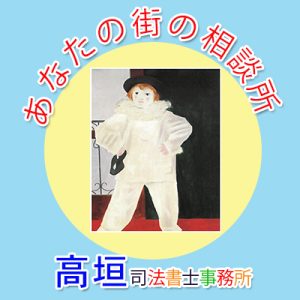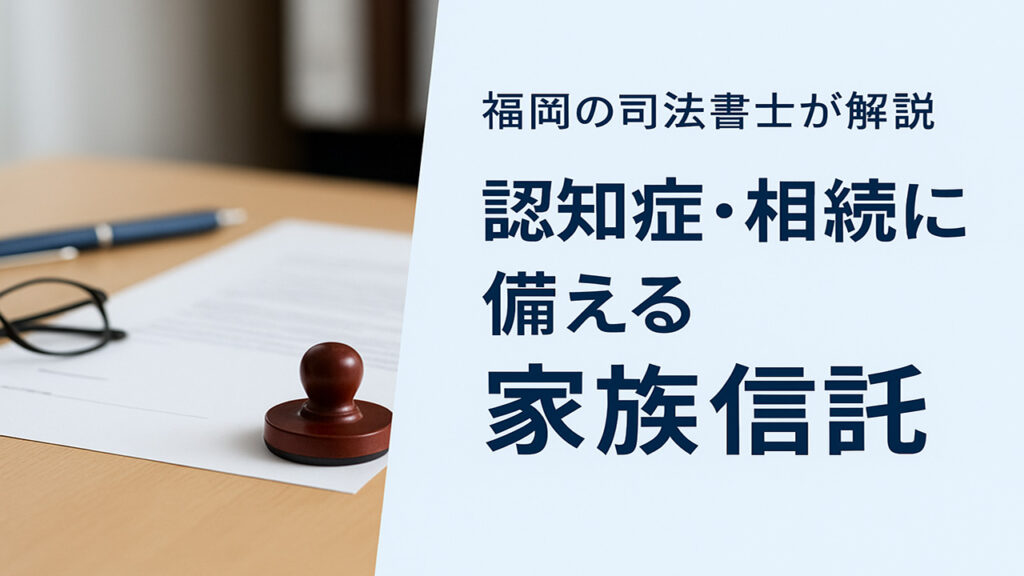家族信託(民事信託)とは?―福岡での認知症対策・相続準備に有効な新しい手段
高齢の親の財産管理や、将来の相続の見通しについて不安を感じていませんか。
「通帳や不動産の管理を手伝いたいが、名義は親のまま」「認知症になったら預金が凍結されると聞いて心配」
「遺言だけで二次相続まで見通せるのか不安」――こうしたお悩みに
家族信託(民事信託)は現実的な解決策を提示します。
本ページでは、福岡市南区大橋の司法書士が、一般の方にもわかりやすく家族信託の基本から活用例まで解説します。
家族信託の基本
家族信託は、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族や第三者(受託者)に 財産の管理・運用・処分を任せ、利益を受ける人(受益者)を定める契約(信託)です。 端的に言えば「委託者・受託者・受益者で財産管理を仕組み化する契約」です。
- 契約で仕組みを設計:誰が・何を・誰のために・どのように管理するかを事前に取り決めます。
- 受託者が法的に管理権限:通帳や不動産の実務管理を受託者が担えるようになります。
- 受益者は利益を受ける人:生活費の支出や不動産からの賃料収入など、実質的な恩恵は受益者に帰属します。
〔主たる信託の目的と信託当事者の例〕
1.老後の生活資金や介護費用に充てる信託(夫婦の老後の安心設計)
委託者:夫A/受益者:本人A・妻B/受託者:本人A/後継受託者:Aの後見開始後に親族Dが就任
2.知的障がいのある長男Bの生活支援(親なき後支援信託)
委託者:親A/第一次受益者:親A・長子B/第二次受益者:次子C/受託者:本人A/後継受託者:Aの後見開始または死亡後に次子Cが就任
3.配偶者なき後の生活を支える設計
委託者(遺言者):夫A/第一次受益者:夫A/第二次受益者:妻B/受託者:旧知の専門職C
4.認知症の配偶者Bの生活支援
委託者(遺言者):夫A/受益者:妻B/受託者:長子C
メリットとデメリット
メリット
- 認知症・判断能力低下への備え:口座凍結リスクを抑え、スムーズな支払い・資産管理が可能。
- 不動産の円滑な管理・承継:老朽化対策、売却・賃貸の判断を家族が迅速に実行。
- 二次相続まで設計可能:受益者を段階的に指定し、将来の承継先まで見通せます。
- 柔軟な運用:遺言や成年後見制度だけでは難しい細かな管理・運用方針を定められます。
- 家族内で完結:制度の運用主体が家族のため、実務のスピードと納得感。
デメリット・留意点
- 設計の難易度:契約内容の不備はトラブルの原因。専門家の関与が重要。
- 受託者の負担:帳簿管理や収支確認など一定の実務が必要。
- 登記・預金の配慮:不動産は信託登記、金銭は信託口口座の開設が必要。
こんな場合に有効です(具体例)
- 認知症対策:将来の判断能力低下を見据え、子が受託者となり生活費・施設費用の支払いを継続。
- 不動産の管理・売却:遠方の親の不動産を子が管理し、必要に応じて修繕・売却・賃貸を実施。
- 二次相続の見える化:配偶者が受益者となった後、二次相続時には子へ受益を承継する設計。
成年後見・遺言との比較
成年後見との違い
- タイミング:成年後見は判断能力低下後、家族信託は元気なうちに準備。
- 柔軟性:後見は厳格な支出管理・家庭裁判所の監督、家族信託は契約で柔軟運用が可能。
- 主体:後見人(第三者)が管理、家族信託は家族が受託者として動ける。
遺言との違い
- 生前の管理:遺言は死後に効力、家族信託は生前から管理・運用が可能。
- 二次相続設計:遺言は一次相続中心、家族信託は段階的な承継を設計。
- 併用が有効:遺言と組み合わせた「遺言信託」では、特定の人に財産を渡し、その人が目的に従い管理・処分する方式を定められます。
家族信託の当事者と役割
- 〔委託者〕
- 受益者の配偶者、受益者の両親・兄弟などの看護者、未成年者の親権者などが該当します。
- 〔受益者〕
- 高齢の委託者本人、高齢または認知症の配偶者、障がいのある子、未成年の子、後妻または内縁の配偶者など。委託者の死亡後に祭祀を行う目的で指定される場合もあります。
- 〔受託者〕
- 親族の中で堅実な人(子、兄弟姉妹、甥・姪など)や、税理士・弁護士・司法書士などの専門職が選ばれるのが一般的です。
- 〔信託監督人〕
- 受託者を監視・監督する第三者。受益者の利益を守るため、必要に応じて裁判上・裁判外の行為を行う権限を有します。
手続きの流れ
- 初回相談:資産・家族構成・目的をヒアリング(福岡市・近郊は来所/オンライン対応可)。
- 設計プランの提示:対象財産、役割分担、受益者範囲、期間、終期、終了後の帰属先を具体化。
- 信託契約書の作成:公正証書で作成。登記の要否も整理。
- 必要な登記・口座開設:不動産は信託登記、金銭は信託口口座を開設。
- 運用開始:受託者による管理・収支記録、定期的な家族内報告。
- 見直し・終了:状況に応じて見直し。終了時は帰属先に従い清算。
よくある質問(FAQ)
Q1:費用はどのくらいかかりますか?
Q2:不動産の名義はどうなりますか?
Q3:家族間トラブルを避けるには?
Q4:どれくらいの期間で始められますか?
司法書士に依頼するメリット
- 実務に即した契約設計:運用しやすい条項設計で現場に強い。
- 不動産の信託登記まで一気通貫:登記の正確性・スピードを担保。
- 家族コミュニケーション支援:合意形成のポイントを整理しトラブル予防。
- 専門家連携:税理士・弁護士・社会福祉士等と連携し総合的にサポート。
福岡南高垣司法書士事務所の特徴(福岡市南区大橋)
- 家族信託・相続・不動産登記に注力:地域事情に通じた実務対応。
- 初回相談で「やるべきこと」を見える化:現状診断・方針案をわかりやすく提示。
- オンライン・出張相談:高齢の親御様がいらっしゃるご家庭にも配慮。
- 明確な費用説明:見積り提示と合意のうえで手続を進めます。
まずはお気軽にご相談ください
家族信託は、「今の安心」と「将来の納得」を両立する有力な選択肢です。
福岡市・春日市・大野城市・那珂川市・太宰府市など近郊エリアのご相談も承ります。
- 無料相談のご予約:TEL:092-516-7151 またはお問い合わせフォームから
- ご準備いただくと良いもの:財産の概要メモ、家族構成、実現したいことのイメージ
迷われている段階でも構いません。初回相談で、最適な準備の進め方をご提案します。