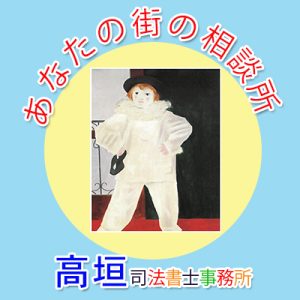B型肝炎訴訟(国との和解手続・給付金請求)
本ページでは、B型肝炎訴訟の全体像・対象判定の目安・次にとるべき一歩を、司法書士がやさしく整理します。
まず知ってほしいこと
- 何から始めれば良いか:①自分が対象か大づかみに確認 → ②必要資料を洗い出す → ③専門家に相談、の順で迷いを減らします。
- 自分が対象か不安:一次感染者(幼少期の集団予防接種等で感染)か、母子感染による二次感染者かをチェック。相続人も対象になり得ます。
- 必要書類が分からない:医療検査結果、予防接種歴、母子感染の有無を示す資料、カルテなどが中心。足りない資料は取得の手がかりから整理します。
ご不安があれば、{{福岡南高垣司法書士事務所}}(092-516-7151 / お問い合わせフォーム)へご相談ください。
B型肝炎訴訟とは(背景と法的枠組み)
かんたんにいうと
幼少期の集団予防接種やツベルクリン反応検査で注射器(針・筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染となった方が、国に損害賠償を求める手続です。
国の責任が認められた流れ(時系列の要点)
- 平成18年:最高裁判決で国の責任が確定。
- 平成23年6月:「基本合意書」成立(全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団と国)→ 救済の要件・金額が整理。
- 平成24年1月13日:特措法(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)施行。
- 平成27年3月27日:「基本合意書(その2)」成立(除斥期間経過の死亡・肝がん・肝硬変への和解枠組み拡充)。
- 平成28年8月1日:特措法の一部改正施行。
- 以後、各地の裁判所で和解手続が進められています。
「訴訟=争う」ではありません
裁判所の仲介で和解(話し合いによる解決)を目指す手続です。証拠をそろえ、要件に合致すれば和解 → 給付金の支給へ進みます。
対象者の概要(一次感染者/二次感染者)
まずはチェック(目安)
一次感染者の目安
- B型肝炎の持続感染がある(HBs抗原やHBV-DNA等で確認)。
- 満7歳になるまでに集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けている。
- 昭和23年7月1日~昭和63年1月27日の国の責任期間に接種歴がある。
- 母子感染ではない。
- 輸血・性交渉・家族内(父等)など他の感染原因が見当たらない。
二次感染者(母子感染)の目安
- 母親が一次感染者の要件を満たす。
- 本人に持続感染がある。
- 母子感染を裏づける資料(出生直後からの感染の資料、または母子のHBV遺伝子配列比較検査など)。
※ 相続人も対象になり得ます(一次・二次感染者本人が亡くなられた場合など)。
認定要件(一次/二次)
一次感染者(5つすべて必要)
- 持続感染があること(例:6か月以上あけた2回の検査でHBs抗原陽性やHBV-DNA陽性等。HBe抗原/抗体の高力価なども参考)。
- 満7歳までに集団予防接種等(予防接種・ツ反)を受けている(最高裁は、幼少期(遅くとも6歳頃)に感染した場合に持続感染になりやすいと判示)。
- 集団予防接種等で注射器の連続使用があったこと(国の責任期間:昭和23年7月1日~昭和63年1月27日。この期間内の接種歴が確認できれば連続使用があったと認められる)。
- 母子感染ではないこと(母親のHBs抗原陰性かつHBc抗体陰性(または低力価陽性)等の検査結果で判断)。
- 他の感染原因がないこと(輸血、父等からの家族内感染、性交渉などが医療記録(カルテ等)に見当たらない)。
二次感染者(3つすべて必要)
- 母親が一次感染者の要件を満たす。
- 本人に持続感染がある。
- 母子感染であること(出生直後からの感染を示す資料、HBV分子系統解析検査での母子の塩基配列の一致など)。
和解までの流れ(4ステップ)
-
1. 準備・提訴
必要な証拠(検査結果、予防接種歴、母子感染の有無、カルテ等)を集め、国を被告として国家賠償請求訴訟を提起。
-
2. 和解協議
裁判所の仲介で話し合い。必要に応じて追加証拠の提出を求められることがあります。
-
3. 和解成立
要件を満たすことが確認できれば和解調書を取り交わします。
-
4. 給付金の請求・支給
和解成立後、社会保険診療報酬支払基金へ給付金等を請求→支給。
当事務所のサポート例
- 必要資料の洗い出し・取得の段取り
- 医療機関への照会文案の整備サポート
- 時系列の整理(接種歴・受診歴・家族歴)
- 弁護士と連携しての訴訟・和解手続の橋渡し
給付金の金額・病態区分(必ず最新情報をご確認ください)
注意:個別事情により金額や要件の当てはめが異なる場合があります。最新の公的情報での照合を前提にしてください。
※ 請求は、これまでの病態の中で最も重いもので行います。
除斥期間とは(超重要ポイントの要約)
- 民法上:「不法行為の時から20年」で損害賠償請求権が消滅する制度。
- 起算点の例:無症候性キャリア=接種日(二次感染者は出生時等)/ 発症(慢性肝炎など)=発症日
- 影響:除斥期間を経過している場合、給付金額が低く設定されます。
無症候性キャリア(除斥期間経過)の政策対応
給付金50万円に加えて、以下の費用が対象(特措法等に基づく)です。
- 定期検査・付随診療の費用(血液学的検査、生化学〈AST・ALT等〉、免疫学、画像〈腹部エコー、造影CT/MRI 等〉)
- 母子感染防止費用(ワクチン・グロブリン投与、検査費用 等)
- 同居家族の水平感染防止費用(ワクチン投与、検査費用)
- 定期検査手当:1回1万5千円(年2回まで定額)
必要書類チェックリスト(最初に集めるもの)
- 持続感染の証明:HBs抗原、HBV-DNA、HBe抗原/抗体(高力価)などの検査結果
- 予防接種歴が分かる資料:母子手帳、自治体記録、学校・職域接種の証跡 等
- 母子感染の有無:母のHBs抗原・HBc抗体の状況、必要に応じHBV分子系統解析検査
- 他原因の否定:輸血歴、家族内感染(父等)、性交渉の医療記録上の痕跡の有無
- 医療機関カルテ:初診日、診断名、採血・画像、治療状況 など
よく詰まるポイントとヒント
- 古い接種歴の裏付け:自治体・学校・保健所の記録照会、家族の記憶・日記・写真など補助資料を組み合わせます。
- 母の検査資料の不足:可能なら現時点での検査、難しい場合は代替資料の検討(専門家へ)。
- カルテが廃棄:診療情報提供書や健診結果、薬剤歴など他資料で補強。
当事務所に依頼するメリット
-
やさしい説明 × 正確
25年の教員経験を活かした分かりやすい説明で不安を軽くします。
-
地域密着と機動力
福岡市南区大橋事務所での対面も、{福岡市内・近郊/全国オンライン対応}も可能。
-
スムーズな段取り
資料取得の手引き、医療機関への照会文案、時系列整理など実務を具体的に支援。
-
当事務所のみで対応可能な場合
簡易裁判所の事件(訴額140万円以下)については、当事務所の認定司法書士が代理人として対応可能です。また、本人訴訟を選ぶ場合は、書類作成支援や手続案内が可能です。
初回相談の流れ
- まずはお電話・フォームでご連絡
- 簡易ヒアリング(対象の可能性・必要資料の確認)
- 資料収集の案内(テンプレの提供や取得先の助言)
- 進め方と費用目安をご説明 → ご納得後に着手
費用の目安(発生タイミング別)
- 初回相談無料
- 資料取得代行:実費+手数料(内容によりお見積り)
- 提訴・和解手続サポート:{{着手金の有無・成功報酬体系}}を明確にご提示
よくある質問(FAQ)
一次感染者と二次感染者、私はどちら?
古い接種歴が証明できません。
相続人でも請求できますか?
期間はどれくらいかかりますか?
医療機関への依頼や照会はどう進めますか?
除斥期間にかかっていそうで不安です。
お問い合わせ(まずは電話相談OK)
お電話:092-516-7151
本ページは一般的な説明であり、個別の事情により結論が異なります。手続・基準・金額は最新の公的情報をご確認ください。
最終更新日:{{2025-10-12}}(厚生労働省『B型肝炎訴訟の手引き』第7版〔令和6年8月改訂〕に基づき作成)
参考情報(公的窓口)
- 厚生労働省 健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室(和解手続等) 専用ダイヤル:03-3595-2252
- 社会保険診療報酬支払基金(和解後の給付金等の請求手続) 給付金等支給相談窓口:0120-918-027